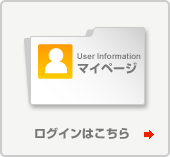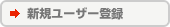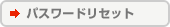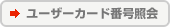2025B期におけるSACLA試験利用の募集について
締め切りました
2025年4月17日
登録施設利用促進機関
公益財団法人高輝度光科学研究センター(JASRI)
X線自由電子レーザー施設SACLAの2025B期の試験利用の定期募集を行います。これは、今後の科学的価値の高い実験の実施を目指して、予めSACLAを試験的に利用していただくものです。
1.募集する試験利用
2.応募資格
3.利用できるビームライン・装置等
4.利用期間・ビームタイム配分
5.利用に係る料金
6.応募に必要な手続き及び注意事項等
7.募集締切
8.審査及び審査結果の通知
9.試験利用実験報告書
10.成果の公開
11.その他
12.お問い合わせ・ご相談先
特記事項
1. 募集対象
下記装置を用いた試料のスクリーニング、及び測定条件・フィジビリティの確認
- シリアルフェムト秒結晶構造解析(SFX)装置DAPHNIS [Tono et al., J. Synchrotron Rad. 22, 532 (2015)]
- マイクロメートル程度の結晶のX線回折計測
- ナノメートルサイズの結晶の粉末X線回折計測
対象となる試料結晶には、蛋白質結晶と物質材料系結晶が含まれます。なお、同期レーザーを用いたポンプ-プローブ実験は対象外です。
- ハイパワーナノ秒レーザー実験プラットフォーム [Inubushi et al., Appl. Sci. 10, 2224 (2020)]
- レーザー衝撃圧縮された数100万気圧下の物質の超高速X線計測
- レーザー照射に伴う流体力学の超高速X線計測
本プラットフォームの利用にあたっては下記の「ハイパワーナノ秒レーザーの利用について」をお読みください。
ただし、実験条件につきましては、スケジュール等の都合上、ご希望に添えない場合があります。
2. 配分ビームタイム
最大1シフト
3. SACLA利用研究課題申請との関係
利用研究課題と試験利用の双方に応募が可能です。
ただし、同一内容で申請する場合は、試験利用の申請を行わず、利用研究課題の申請時に「5.試験利用との併願」の該当箇所にチェックを入れてください。利用研究課題として不採択となった際には、試験利用として審査をうけることができます。
4. 成果公開
利用研究課題とは異なり、査読付論文等の公開義務はありません。第9項に記載の試験利用実験報告書の提出が義務づけられます。提出された報告書はWeb公開されます。
5. ハイパワーナノ秒レーザーの利用について
SACLAでは、大阪大学が中心となってハイパワーナノ秒レーザー(HERMES)の整備が行われました。このレーザーとXFELとの同時利用実験を実施するため、XFELの集光光学系や実験チャンバーなどを含む実験システムがBL3 EH5において整備されています。
この実験システムを利用した、ハイパワーナノ秒レーザーとXFELの同時利用実験に関する試験利用については、下記事項に同意のうえ申請してください。
- 試験利用が採択された場合、JASRIは試験利用の情報を大阪大学レーザー科学研究所に通知します。
- 利用研究成果の公開には、SACLA及び大阪大学レーザー科学研究所のハイパワーナノ秒レーザーを使用した成果と明記する必要があります。
この実験システムの利用を希望するユーザーは、申請前に必ずXFEL利用研究推進室 (sacla-bl.jasri@spring8.or.jp)まで、レーザー及び実験システムの運用条件についてお問い合わせください。
なお、2024B期における典型的なレーザー運用条件は、以下の通りでした。
- パルスエネルギー:15 J程度(サンプル上において)
- パルス波形:5 ns(矩形波)
- 中心波長:532 nm
- 集光ビームプロファイル:回折型ホモジナイザーを利用した、トップハットプロファイル(120、170、260または470 µm FWHM程度。)
〈2025B期募集に関する重要事項〉
○実施可能性に関する事前問い合わせについて
計画されている実験の実施可能性についてご不明な点がある場合には、XFEL利用研究推進室(sacla-bl.jasri@spring8.or.jp)までご相談ください。事前の問い合わせを行い、実施可能性について施設側研究員の回答を受けた場合には、その回答結果について申請書内に記載ください。
○共同実験責任者の指定について
実験責任者(試験利用申請者)が希望する場合は、試験利用申請時に共同実験者の中から「共同実験責任者」を指定可能です。共同実験責任者は、実験責任者と共同で責任を持って試験利用を主導いただける方とし、そのため、実験責任者と同様に試験利用の応募資格を有している方に限られます。共同実験責任者の役割の具体例を以下に示します。
- 対象となる装置・手法・技術などに精通しており、複数の関連一般課題や試験利用の実施を統括する。
- 実験責任者に代わって施設との連絡窓口となり、施設側担当者との情報交換を責任を持って行う。
なお、共同実験責任者として施設側研究員を指定することも可能です。
共同実験責任者を指定するには、申請書に以下の通り記載してください。
- 記載場所:「研究の提案理由」欄
- 記載内容:共同実験責任者のユーザーカード番号、氏名、所属機関名
○関連する他の課題または試験利用申請からの一部引用について
関連課題または試験利用との関係性を明確にし、申請書の効率的な作成を可能にするため、過去に申請済みまたは同時期に申請予定の課題または試験利用と内容が共通する部分については、以下の条件のもとで申請書の記述を一部引用することが可能です。ただし、引用にあたっては、引用元となる申請と引用先となる申請(本申請)の違いを必ず明記してください。
- 引用元となる申請の実験責任者が、本申請の実験責任者または共同実験者であること。
- 引用元となる申請の情報(実験責任者名や課題番号など)が明記されていること。
- 引用は、例えば「研究の提案理由」欄中の研究の背景、「実験の方法」欄中の測定法・レイアウトなど、それぞれの記載項目欄内の一部に限定されていること。
- 各申請書内の記述だけに基づいて審査を行えるよう、必要な情報が個別の申請書内に漏れなく含まれていること。
1.募集する試験利用
2025B期は、以下を募集します。
- 対象装置を用いた試料のスクリーニング、測定条件・フィジビリティの検討
有効期間は当該2025B期のみとなります。
2.応募資格
基本的に制限はありませんが、以下にご留意ください。
- ○海外の機関に所属する方※
実験責任者としての応募は可能です。但し、コンタクトパーソン(利用に係る手続き、JASRIからの問い合わせ等に対し対応が可能な方)として、日本国内の機関に所属する方1名以上の共同実験責任者または共同実験者の参画を義務付けます。適切なコンタクトパーソンが見当たらないような場合は、試験利用申請前に利用推進部(sacla.jasri@spring8.or.jp)までお問い合わせ又はご相談ください。
※日本国外にある機関に在籍し、SACLA利用の際は海外から来訪される方 - ○学生の方
実験責任者としての試験利用の応募はできません。なお、共同実験者として参画することは可能です(共同実験責任者としての参画はできません)。
3.利用できるビームライン・装置等
試験利用で利用可能なビームラインと利用可能な装置は以下の通りです。ただし、使用できる装置の条件などについては、本募集案内中の特記事項もご確認ください。
- ○利用可能なビームライン
- ・BL3(XFELビームライン1)
- ・BL2(XFELビームライン2)
- ○利用可能な装置
- ・シリアルフェムト秒結晶構造解析(SFX)装置DAPHNIS
- ・ハイパワーナノ秒レーザー実験プラットフォーム
詳細は「ビームライン情報」をご覧ください。
4.利用期間・ビームタイム配分
2025年10月より2026年3月(予定。この間の施設メンテナンスによる調整期間等を除く)において、当該期間中の施設運転を24時間連続で行い、利用時間(ビームタイム)を利用者へ提供します。
また、試験利用ごとのSACLAのビームタイム配分は、最大1シフト(12時間)となります。なお、予算状況等により利用期間が変更になる場合がありますので、予めご了承ください。
5.利用に係る料金
試験利用については、利用料金の負担はありません。
6.応募に必要な手続き及び注意事項等
試験利用の応募(申請)は、SACLA UIサイト(SACLA User Information Website)を利用して申請を行っていただきます。
1.ユーザー登録
試験利用を申請するためには、事前にSPring-8・SACLA共通のユーザー登録が必要となります。申請者(実験責任者)・共同実験者を含めて、未登録の方は当該Webサイトからご登録ください。
2.申請
【申請方法】
試験利用の申請はWebサイトを利用した電子申請で受け付けます。
申請方法の詳細については、SACLA利用研究課題と同様となりますので、「SACLA 利用研究課題オンライン入力要領」をご参照ください。
【申請書作成について】
申請書作成に際しては、下書きファイルを用意しています。下書きファイルには課題申請に必要な記入項目と補足事項が示されており、申請書作成の手引きとなりますので、ご利用になることを強く推奨します。
試験利用の申請は、実験責任者が行ってください。申請書提出後は、共同実験者も閲覧が可能となります。
3.応募受理通知
申請完了後、SACLA試験利用申請受理通知と応募者控え用の誓約事項のPDFファイルがメールで送付されます。メールが届かない場合は申請が受理されていない可能性がありますので、以下の通り確認してください。
UIサイトからマイページにログインし、メニュー(画面左側)の 課題申請書>提出済 をクリックしてください。( トップページ > ログイン > 申請/報告 > 課題申請書 )
- 申請が「提出済」に表示されていない場合:
受理されていません。もう一度申請の「提出」操作を行ってください。 - 申請が「提出済」に表示されている場合:
受理されています。ユーザー登録内容が正しいにもかかわらずメールが不着となっている場合は、利用推進部(sacla.jasri@spring8.or.jp)までお問い合わせください。
その他
- ○試験利用の有効期間について
採択されたSACLAの試験利用は当該利用期間(2025B期)に限り有効です。当該利用期間内に実行できる範囲の具体的な研究内容で申請してください。 - ○実験責任者について
実験の実施全体に対して責任を持つことができる方が実験責任者となってください。
7.募集締切
2025年5月23日 (金) 午前10時 JST(UTC+9 申請書類の提出完了時刻)
電子申請書の作成(入力)は時間的余裕をもって行っていただきますようお願いいたします。
Web入力に問題がある場合は、利用推進部へ連絡してください。応募締切時刻までに連絡(締切日当日に限る)を受けた場合のみ別途送信方法のご相談に応じます。
8.審査及び審査結果の通知
1.審査
倫理性、実験の実施可能性および実験の安全性について総合的かつ専門的に審査します。
(1) 提案試験利用の実施及び成果の利用が平和目的に限定される等、科学技術基本法や社会通念等に照らして、当該試験利用の実施が妥当であること
(2) 実験内容の技術的な実施可能性
(3) 実施内容の安全性
試験利用課題全体の配分ビームタイムには上限があります。
2.審査結果の通知
審査結果(申請の採否)は、2025年8月上旬(予定)に電子メールにて通知いたしますので、User Informationマイページにログインの上、ご確認ください。
9.試験利用実験報告書
試験利用の実施の透明性を確保するため、試験利用終了後60日以内に、実施概要の報告をお願いします。(分量はA4版1ページ以内、言語は英語又は日本語、記載内容は、研究の目的、実験方法、測定内容、試料名、結果の概要)。提出された試験利用実験報告書は、ユーザータイム終了後60日目から2週間後にWeb公開します。試験利用実験報告書の詳細は、SACLA利用研究課題と同様となりますので「こちら」をご覧ください。
記載内容についてのご相談は、利用推進部(sacla.jasri@spring8.or.jp)までお問い合わせください。
10.成果の公開
試験利用実験報告書以外の成果の公開は義務ではありませんが、以下のいずれかにより成果を公開する場合は、1. 謝辞を記載したうえで、2. 研究成果データベースにて成果のオンライン登録を行ってください。詳細は、「成果公表」の該当箇所をご覧ください。
- 整理番号が明記されている査読付き論文(査読付きプロシーディングス、博士学位論文を含む)
- SPring-8/SACLA利用研究成果集
- 公開技術報告書
成果公開の詳細は、SACLA利用研究課題と同様となりますので「成果公表」をご覧ください。
11.その他
- 放射線業務従事者登録
利用者は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(法律第167号)に従い、放射線業務従事者登録が必要となります。詳細は、「提出書類詳細」をご覧ください。 - 単独実験・作業の禁止
実験の安全上の観点から、原則として単独での利用はできません。共同実験者を確保した上で応募(実施)してください。 - 装置の故障、災害発生時および伝染病発生時の措置
状況により、課題採択後のビームタイムを利用できない場合があります。その場合、ビームタイムの補償はできかねますことを予めご了承ください。 - 損害保険の加入および賠償責任について
利用実験実施等に際し、不慮の事故に備えて傷害保険および賠償責任保険またはこれらと同等の保険に加入していただく必要があります。また、故意または重大な過失によってSACLAおよびSPring-8ならびにそれらに附属する施設、設備ならびに物品その他に損害を及ぼしたときは、損害の全部または一部を賠償していただく場合があります。
12.お問い合わせ・ご相談先
利用制度その他全般に関するお問い合わせ・ご相談
〒679-5198 兵庫県佐用郡佐用町光都1-1-1
公益財団法人高輝度光科学研究センター(JASRI) 利用推進部
TEL:0791-58-0961
e-mail:sacla.jasri@spring8.or.jp
利用研究に係る技術的お問い合わせ・ご相談
産業界の皆様からのお問い合わせも是非お待ちしております。
〒679-5198 兵庫県佐用郡佐用町光都1-1-1
公益財団法人高輝度光科学研究センター(JASRI) XFEL利用研究推進室
e-mail:sacla-bl.jasri@spring8.or.jp