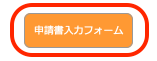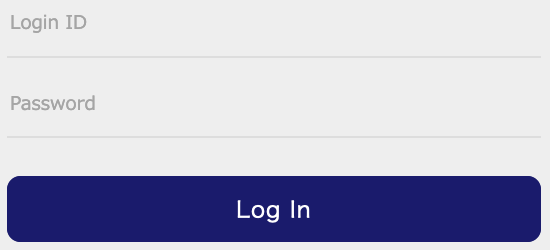- 来所前の提出物
- 実験後の提出物
- その他の手続
| 来所前の提出物について |
■放射線業務従事者等登録手続〈提出:全員(来所者,遠隔実験システム利用者)〉他
提出期限:年度初回来所の10日前
SPring-8/SACLAの放射光を利用される方は、年度毎に理研播磨地区での放射線業務従事者登録が必要です。登録が完了しないと実験に参加できませんのでご注意ください。
申請書の承諾期間終了日を年度末日にした場合、同一年度の再来所において放射線業務従事者登録の再手続きは必要ありません。
- [2022年1月より]SPring-8及びSACLAにおける放射線業務従事者等の登録・変更・中止等の各種手続がペーパーレス・押印レス化されました。詳細は以下をご覧下さい。
放射線業務従事者登録等手続きのペーパーレス化について - [2024年度より]所属機関に放射線取扱主任者がいない場合に限り、労務管理者の記載が可能となりました。詳細は、以下をご覧ください。
https://harimariken01.spring8.or.jp/procedure/info/20240122.pdf - [2025年度より]労務管理者による放射線作業者登録申請(日本国内機関のみ)においてもペーパーレス化に対応することとなりました。詳細は、以下をご覧ください。
https://sacla.xfel.jp/?p=19313 - [2024年度より]SPring-8/SACLA来所時に、所属元の個人被ばく線量計の持参が必須ではなくなりました。詳細は、以下をご覧ください。
https://harimariken01.spring8.or.jp/procedure/info/20240122.pdf
様式
「PDF・紙 *」と「ペーパーレス(推奨)」の2通りから選択できます。理研播磨事業所のWebページより登録手続きをお願いします。
理化学研究所 播磨事業所 安全管理室Webサイト
* 郵送または、カラースキャンしたPDFデータのメール添付での提出が可。
<所属機関に放射線取扱主任者がいる場合>
所属機関承諾・証明欄に、申請者の被ばく線量記録、放射線の教育訓練の受講記録および、電離放射線健康診断結果を記録管理している部署の放射線取扱主任者*の記名および押印をお願い致します。(「ペーパーレス」申請では押印不要。)
* 放射線取扱主任者とは、事業所で選任されている主任者で、資格のみの保持者は含まれません。
<所属機関に放射線取扱主任者がいない場合>
所属機関承諾・証明欄に、労務管理者*の記名および押印をお願い致します。(「ペーパーレス」申請では押印不要。)申請書に「放射線教育訓練受講日」と「電離放射線健康診断受診日」の記載、および安全管理室Webサイトより「電離放射線健康診断の写し」のアップロードが必要です。詳細は下記リンク先をご参照ください。
「放射線作業者登録申請書」における労務管理者申請のペーパーレス開始についてのお知らせ
* 労務管理者とは、労務を担当する部署の責任者で、機関の代表者・部門長・部長等労務上の責任者。
<海外の機関に所属する方>
所属機関承諾・証明欄に、自国の法令等に基づいて申請者の被ばく線量、放射線の教育訓練の実施および健康診断結果を記録管理されている方の記名および押印 (署名可)をお願いします(「ペーパーレス」申請では押印・署名不要)。
手続きの流れ
手続きの詳細
放射線Web申請による放射線業務従事者登録に関するQ&A
放射線教育訓練機関
所属機関で放射線教育訓練を受講できない場合は、下記の安全教育訓練実施機関等をご利用ください。
【参考】安全教育実施機関:
- (公社)日本アイソトープ協会 tel. 03-5395-8081 https://www.jrias.or.jp/
- (株)千代田テクノル tel. 03-3816-2931 https://www.c-technol.co.jp/education
- (公財)放射線計測協会 tel. 029-282-5546 https://www.irm.or.jp/
理研播磨地区放射線安全教育(e-ラーニング)
放射線作業者登録申請書の受理後、理研播磨地区放射線安全教育(e-ラーニング)を受講して頂きます。受講完了後、従事者として登録されます。e-ラーニングの詳細については、こちらをご覧ください。
中止手続き
登録中に所属が変更になった場合は、速やかに「放射線業務従事者等中止手続」をお願いします。中止手続後の利用に関しては、再度、変更後の所属から放射線業務従事者等登録手続が必要です。
お問い合わせ(全般)・書類提出先
〒679-5198 兵庫県佐用郡佐用町光都1-1-1
(公財)高輝度光科学研究センター 利用推進部 共用推進課
Tel: 0791-58-0961 Fax: 0791-58-0965
e-mail: uoffice@spring8.or.jp
お問い合わせ(専門的事項・入力エラー等)
国立研究開発法人理化学研究所 播磨事業所安全管理室放射線管理受付
Tel: 0791-58-0904 Fax: 0791-58-0932
e-mail: radiationsafety@spring8.or.jp
■e-ラーニングによる放射線安全教育(2019年度より)
各年度初回来所前に、SPring-8/SACLAにて放射線業務従事者登録を行うために放射線安全教育を受講していただきます(通常、年度内再来所の方は不要)。
下記の手順により、受講いただきますようお願いいたします。
①放射線業務従事者等登録手続*1
・理研播磨事業所安全管理室Webページよりオンラインで放射線業務従事者等登録手続をお願いします。
※Web申請の場合は個人ページにログインいただくと申請書の進捗状況、ならびにe-ラーニングの受講状況が確認出来ます
・受講者情報が、SPring-8/SACLAの放射線安全教育管理システムへ登録されます。
②放射線安全教育[e-ラーニング]の受講案内*(Eメール)
・理化学研究所播磨事業所安全管理室より、上記登録時のEメールアドレスにお送りします。
・Eメールに記載された受講URLにアクセスして受講してください。
・パスワードは放射線業務従事者等登録時の受付番号となっております。
③ e-ラーニングによる放射線安全教育の受講
・使用環境は下記*2のとおりです。
・受講完了後、「受講済」情報が、放射線安全教育管理システムに反映されます。
④SPring-8/SACLAへの実験来所
・北管理棟受付(19:30以降は正門守衛所)にお越しください。
・ユーザーカードと線量計をお渡しします。
・e-ラーニング受講済の場合は、現地で安全講習を受講していただく必要はありません。
*(年度初めての来所の方)夜間の正門守衛所での受け取りを希望の場合は当日午前8時までにe-ラーニングの受講を完了してください。
*1注意事項
・記入漏れなどがある場合は、e-ラーニングによる受講が出来ませんのでご注意ください。
・e-ラーニングによる受講が出来ない場合は、来所後に放射線安全教育を受講していただきます。
| OS | Windows 10, 11 | |
| Mac OS | ||
| ブラウザ | Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox, Safari 最新版のブラウザを使用してください |
|
| 再生 | HTML5プレーヤー(Flash Playerプラグインは不要となりました) | |
■ 化学実験安全テキスト
SPring-8/SACLAで実施される研究の安全確保を目的として、化学実験を行う施設利用者の皆様に共通の安全認識やルール等の理解を深めていただくためのものです。
関係者全員、これらテキストをご一読ください。
化学物質の取扱いについて(第2版)
■ 利用申込書(オンライン) 様式10〈提出:実験責任者〉
実験責任者および共同実験者の来所申込をするための書類です。研究交流施設の申し込みを兼ねています。
必ず来所の10日前までに提出してください。
利用申込書には、SACLAへの来所者に加えて、web会議でのオンライン参加者と遠隔実験システム利用者も記載してください。来所種別で「来所」「オンライン参加」「遠隔操作」を選択してください。
ご提出後、内容の修正等がない場合も含め、担当より確認メールをお送りいたします。届かない場合は、「迷惑メールフォルダ」等をご確認ください。それでも届いていない場合は、利用推進部(uoffice@spring8.or.jp)までお問い合わせください。
- マイページにログイン後、『利用申込書』にユーザーカード・線量計受取/返却日時および研究交流施設利用期間を記入のうえ、オンライン提出してください。
- 他の課題等で既に予約済みの場合や、利用をしない場合は“交流施設を利用しない”にチェックを入れてください。
- なお、来所しないユーザーについては、“除外”にチェックを入れてください。
注意事項:
- 2つの課題の日程が重なっている場合は、課題毎に提出が必要です。
- 現在、事前提出書類のうち3種類(利用申込書、試料および薬品等持込申請書、物品持ち込み届 — 物品を持ち込む方のみ)がオンライン提出となっていますが、最初に「利用申込書」を提出してから他の2種類の申請書をご提出ください。「利用申込書」を提出するまで、他の2種類の書類は提出できませんのでご注意ください。
- 提出後に変更が生じた場合は、利用推進部までメールにてお知らせください。
■ 試料および薬品等持込申請書(オンライン) 様式9〈提出:実験責任者〉
SPring-8/SACLAで使用する試料や薬品の「持ち込み」から「持ち出し」の状況を確認するための書類です。マイページにログイン後、『試料および薬品等持込申請書』に入力し、必ず持込日の10日前までにオンライン提出してください。「試料および薬品等持込申請書」には、SPring-8/SACLAに持ち込む全ての試料、薬品(洗浄や保存のために用いる溶媒、ガスも含む)の名称(略称、記号等には説明)、形態(形状)、量(単位も記入)、性質(危険有害性)、用途、持ち込み期間、安全対策、リスクレベルを記述してください。リスクアセスメントの詳細は、「化学物質リスクアセスメントについて」をご覧ください。提出された申請書の記載内容について安全上の疑義が生じた場合には、安全管理室よりご連絡いたしますので、必要な情報の提供にご協力をお願いいたします。試料や薬品を持ち込まない場合は、“持ち込み試料/薬品なし”にチェックを入れてください。チェックがない場合は提出できません。なお、毒物、劇物および有機溶剤等の危険物・有害物質を持ち込む場合は、来所時に必ずビームライン担当者にその旨を伝えてください。
注: 「利用申込書」が提出されるまで「試料および薬品等持込申請書」は提出できませんのでご注意ください。 提出後に変更が生じた場合は、利用推進部 までメールにてお知らせください。
■ 貨物の送付について
実験に必要な試料、薬品、貨物を宅配で送る場合、ユーザー自身で受取れるよう手配をお願いします。自身で受取ることができない場合は、利用推進部宛気付で送付することができます。宛先には下記のように受取人本人の名前、課題番号を記入してください。
詳細は、こちらのページをご覧ください。
<宛先>
〒679-5198 兵庫県佐用郡佐用町光都1-1-1
(公財)高輝度光科学研究センター
利用推進部気付 SACLA共用実験ユーザー○○○○様 (課題番号 2021A####)
TEL: 0791-58-0961
2021A期より、海外貨物については、発送時・返送時に発送連絡メールをお願いします。
また、輸入規制品や採択時の安全審査コメントへの対応をお願いします。
詳細は、こちらのページをご覧ください。
■ 物品持ち込み届(オンライン) 様式8〈提出:実験責任者〉
大型の測定装置や周辺機器等の利用実験に係る物品を、SPring-8/SACLAに持ち込む(宅配便等を利用する場合も含む)必要がある場合には、必ず来所の10日前までに、マイページから『物品持ち込み届』に必要事項を入力し、オンライン提出してください。持ち込みを計画されている装置や機器については、それらが安全かつ正常に機能することを所属機関などにおいて事前に試験し確認した上で、SPring-8/SACLAに持ち込むようにしてください。なお、危険物や規制品など安全上の問題がある場合は持込ができない場合がありますのでご注意ください。
注:「利用申込書」が提出されるまで「物品持ち込み届」は提出できませんのでご注意ください。 提出後に変更が生じた場合は、利用推進部までメールにてお知らせください。
■ 貨物の送付について
2021A期より、海外貨物については、発送時・返送時に発送連絡メールをお願いします。
また、輸入規制品や採択時の安全審査コメントへの対応をお願いします。
詳細は、こちらのページをご覧ください。
| 実験後の提出物について |
■ ビームタイム終了届 (ビームタイム利用報告書)(オンライン) 様式12〈提出:実験責任者および共同実験者〉
来所ごとに利用状況を報告するものです。実験後マイページよりご提出ください。 利用時間、SPring-8/SACLAで供給した液体ヘリウムおよびヘリウムガスの使用量は、消耗品費の実費負担額の確定のための基礎データとします。また、次回の利用者に対するアドバイス、施設に対する要望や提案もお書きください。施設へのご要望等につきましては検討のうえ原則として回答を添えてビームタイム終了届(ビームタイム利用報告書)検索にて公開します。
■ 利用課題実験報告書(オンライン) 様式26〈提出:実験責任者〉
実験責任者は、一連の実験についての解析結果を取りまとめた、利用実験課題報告書(様式26)を、利用研究課題終了後60 日以内にマイページからオンライン提出してください。実験責任者のアカウント(ユーザーカード番号およびパスワード)でマイページにログイン後、メニューから「利用課題実験報告書」を選択すると、利用課題実験報告書の入力ページが表示されます。記入要領は こちら をご覧ください。
成果公開と見なされるには、課題実施期終了後3年以内に査読付き論文等を発表し、SPring-8研究成果データベースに登録する必要がありますのでご注意ください。
提出された利用課題実験報告書は、各期終了後60日目から数えて2週間後にUIサイト上で公開されます。
| 高出力レーザを使用する場合の手続き等について |
SACLAでの利用実験課題を実施するために高出力レーザ機器を使用する場合、以下の必要な手続き等を行ってください。
(1)高出力レーザ機器を一時的に持込み、使用する場合
- 実験責任者は【様式24-1】高出力レーザ機器一時持込み及び使用届 を、当該機器設置2週間前までにJASRI安全管理室※(safety@spring8.or.jp)へ提出(原本不要、PDF可)。※2022年1月より
- 持込みレーザ機器のレーザ管理区域に立ち入る全ての者は、レーザ機器管理者(実験責任者)からレーザ取扱いに関する安全指導を受けてください。
- 「高出力レーザ機器一時持込み及び使用届」【様式24-1】については、同一年度内の使用においても都度提出が必要となります。
[手続き]
様式24-1については、以下の安全対策を遵守し提出すること。
1.クラス3Rのレーザには、以下の各号に掲げる安全対策を施す。
(1)管理区域を設定し、標識を掲示する。
(2)レーザを設置する区域の入口に、使用されるレーザの性能と、取扱上の注意事項を掲示する。
(3)適切な保護具を着用する。
(4)レーザ光路は作業者の目の高さを避け、不透明で不燃性の強固な材料により遮蔽する。
(5)制御盤には、システムキーを設ける。
(6)レーザを照射中もしくはレーザの照射が可能な状態では、警告灯が自動的に点灯すること。
2.クラス3B、クラス4のレーザには、クラス3Rの安全対策に加えて以下の各号に掲げる
安全対策を施す。
(1)緊急停止ボタンを設ける。
(2)レーザの照射口にシャッターを設ける。
(3)電気的、物理的なインターロックを設ける。
(4)レーザ光路には、耐火構造の終端部を設け、反射光や散乱光に対する遮蔽をする。
(5)レーザ設置後、安全管理室立会いの下でインターロック試験を実施する。
(2)SACLA常設の同期レーザシステムを使用する場合
- レーザ管理区域に立ち入る全ての者は、SACLA常設レーザ安全web講習を受講してください。(各年度ごと初回使用時のみ:各年度とも4月1日以降に受講可能)
- 上記常設レーザ安全web講習は、SACLAマイページ※のサイドメニュー「常設レーザ安全講習」ページより受講いただけます。安全講習ビデオ視聴後、受講完了ボタンをクリックしてください。
マイページ > 申請/報告 > 来所前 > 常設レーザ安全講習
※SACLA用講習は(SPring-8マイページではなく)SACLAマイページです。 - 実験責任者は課題実施前までに、自身の課題でレーザ管理区域に立ち入る共同実験者がレーザ安全講習を受講していることを利用申込書ページから必ず確認してください。
マイページ > 申請/報告 > 来所前 > 利用申込書 - 利用申込書に共同実験者の受講状況が表示されていない場合は、当該実験が常設レーザ使用課題に登録されておりません。実験責任者の方は、JASRI安全管理室(safety@spring8.or.jp)に常設レーザ機器を使用する旨を課題番号と合わせてご連絡ください。
| 高圧ガス容器持込みについて |
■ 高圧ガス容器持込事前申請書 様式25〈提出:実験責任者〉
課題申請に基づき、SACLA実験研究棟へ「高圧ガス容器」を持込む場合は、持込日40日前には
「高圧ガス容器事前持込申請書」【様式25】![]() をJASRI安全管理室(safety@spring8.or.jp)に提出をお願いいたします。
をJASRI安全管理室(safety@spring8.or.jp)に提出をお願いいたします。
現在、SACLA実験研究棟は、高圧ガスの貯蔵量が300m³未満であり、高圧ガス保安法の「第二種貯蔵所」には該当していません。
しかしながら、現状の貯蔵量が300m³に逼迫しており、新たに「高圧ガス容器」をSACLA実験研究棟内へ持込む場合は、その持込量を管理し、総量として300m³を超えない事が持込許可の条件となります。持込みに際しては、出来るだけ小容器にてお願い致します。
尚、提出された「高圧ガス容器持込事前申請書(ユーザー用)」の内容は、「持ち帰り年月日」を期限として、総量から削除されますのでご注意願います(ビームタイムが複数回ある場合、本申請書もビームタイム毎に提出願います)。
| 生物試料を用いる実験に係る手続き等について |
■ 生物系実験安全テキスト
SPring-8/SACLAで実施される研究の安全確保を目的として、生物系実験を行う施設利用者の皆様に共通の安全認識やルール等の理解を深めていただくためのものです。
関係者全員、これらテキストをご一読ください。
生物系実験について(第2版)
SPring-8/SACLAで生物試料を用いる実験を行う際は、事前の承認が必要です。定められた期日までに、以下の必要な書類を利用推進部に提出してください。
| 微 生 物 実 験 |
■ 生物実験計画届 様式19-1〈提出:実験責任者〉
微生物(細菌、ウィルス、真菌、寄生虫、感染性を持つ核酸、プラスミド等)およびそれらに汚染された材料を用いて実験する場合は、事前の承認が必要です。年2回のSACLA利用研究課題の審査結果通知後2週間以内に、「生物実験計画届」を別途安全管理室まで郵送してください。
詳細については、こちらを参照してください。
| 遺 伝 子 組 換 え 実 験 |
遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成15年法律第97号)」に定められている遺伝子組換え実験を行う際は、事前に次の手続きが必要です。遺伝子を組換えた生体の持込みも含みます。
公益財団法人高輝度光科学研究センター(以下、「JASRI」)で実施できる実験
| 第一種使用等 | ||||||
| 第二種使用等 | 遺伝子組換え実験 | 微生物使用実験 | P1 | P2 | P3 | |
| 大量培養実験 | LSC | LS1 | LS2 | |||
| 動物使用実験 | P1A | P2A | P3A | 特定飼育区画 | ||
| 植物等使用実験 | P1P | P2P | P3P | 特定網室 | ||
| 細胞融合実験 | ||||||
 遺伝子組換え実験承認申請
遺伝子組換え実験承認申請
 遺伝子組換え実験従事者登録について
遺伝子組換え実験従事者登録について
 実験開始前〜実験終了までの手続き
実験開始前〜実験終了までの手続き
①遺伝子組換え実験承認申請(対象:実験責任者)
JASRIで遺伝子組換え実験を行う場合は、事前に承認を受ける必要があります。実験責任者*は下記の手続きを行ってください。
*実験責任者となる者は、遺伝子組換え実験の経験を1年以上有するもので、必ずJASRIに来所し、実験に携わる者とする。原則として、学生は不可。
課題申請手続きの流れ
〈申請書提出〉
遺伝子組換え実験承認申請書【様式20-1】![]() を指定された期日までに安全管理室へ郵送してください。
を指定された期日までに安全管理室へ郵送してください。
※締切に間に合わなかった場合は、実験できない場合があります。
※実験計画を立てる際は、実験が「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成15年法律第97号)」及び関係法令に適合するように十分検討してください。
〈安全性の審査〉
提出された資料をもとに、取り扱い方法や設備面等も含めて、安全委員会で安全性を審査します。
実験責任者(代理者可)には、安全委員会に出席していただき、実験内容についてヒアリングを行う場合があります。
〈承認の通知〉
実験実施の可否は、通常、遺伝子組換え実験安全委員会の審査から1ヶ月以内に書面にてお知らせします。
承認を受けた実験課題の有効期限は原則3年間です。
②遺伝子組換え実験従事者登録(対象:実験に従事する者)
遺伝子組換え実験に従事しようとする者は、遺伝子組換え実験従事者としての登録手続きが必要です。登録には、教育訓練や健康診断の実施、書類の確認等が必要ですので、早めに申請して下さい。
◇ 登録
遺伝子組換え実験従事者申請書兼誓約書【様式20-5-3】![]() を安全管理室宛に郵送してください。
を安全管理室宛に郵送してください。
※教育訓練受講の終了と必要書類の提出が確認できた者を、遺伝子組換え実験従事者として登録しますので、手続きは早めに行ってください。
◇ 更新
遺伝子組換え実験従事者登録の有効期間は年度末までとなっていますので、次年度も遺伝子組換え実験に従事される場合は、年度末に更新手続きを行ってください。更新手続きは、新規手続きと同じです。
◇ 実験従事者終了
年度の途中で遺伝子組換え実験従事者登録を終了したい場合、以下の手続きを行ってください。
遺伝子組換え実験従事者終了届【様式20-6-3】![]() を安全管理室へ郵送してください。
を安全管理室へ郵送してください。
◇ 登録内容の変更
実験従事者の所属機関(部署等)が変更した時は、一旦終了手続きを行い、再度登録申請を行って下さい。
③実験開始前〜実験終了までの手続き(対象:実験責任者)
実験開始前(〜随時)
《実験従事者届と実験課題毎の教育訓練》
実験責任者は、実験に従事する遺伝子組換え実験従事者*を指定し、実験開始前にそれらの者に教育訓練を実施してください。教育訓練が終了したら、実験開始の10日前までに 遺伝子組換え実験従事者(届出書/変更届出書)兼教育訓練実施報告書【様式20-7】![]() を安全管理室へ郵送してください。
を安全管理室へ郵送してください。
*事前に遺伝子組換え実験従事者として登録されている者に限ります。
《遺伝子組換え生物等の搬入および搬出》
遺伝子組換え生物等をJASRIに搬入、またはJASRIから搬出する場合は、事前に 遺伝子組換え生物等(搬入・搬出)届出書【様式20-2-2】![]() を提出し(郵送)、安全管理室の確認を受ける必要があります。その際、「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律に基づく情報提供文書*」【様式20-2-1】
を提出し(郵送)、安全管理室の確認を受ける必要があります。その際、「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律に基づく情報提供文書*」【様式20-2-1】![]() を添付してください。
を添付してください。
搬入または搬出の10日前までに、安全管理室へ原本を郵送してください。
10日前までに提出されなかったとき、遺伝子組換え生物等を搬入/搬出できない場合があります。
*情報提供文書は、遺伝子組換え生物等の搬入元機関から必ず入手してください。書式は自由ですが、必要な項目が満たされていない場合は受付できません。詳細は、「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律に基づく情報提供」【様式20-2-1】![]() を参考にしてください。
を参考にしてください。
実験課題承認期間中
《経過報告》
実験実施期間中は、年1回 遺伝子組換え実験(経過・終了)報告書【様式20-3】![]() を提出していただきます(原本)。
を提出していただきます(原本)。
実験終了時
実験を終了する場合は、遺伝子組換え実験(経過・終了)報告書【様式20-3】![]() を安全管理室宛てに郵送してください。次の新たな遺伝子組換え実験実施の計画があり、引き続き実験を行うため遺伝子組換え生物等を保管する場合は、併せて 遺伝子組換え生物等保管場所届【様式20-4】
を安全管理室宛てに郵送してください。次の新たな遺伝子組換え実験実施の計画があり、引き続き実験を行うため遺伝子組換え生物等を保管する場合は、併せて 遺伝子組換え生物等保管場所届【様式20-4】![]() も安全管理室へ提出して下さい(原本)。尚、保管している遺伝子組換え生物等を再び使用する時は、新たに実験の申請が必要です。
も安全管理室へ提出して下さい(原本)。尚、保管している遺伝子組換え生物等を再び使用する時は、新たに実験の申請が必要です。
その他の手続き
《実験材料(供与核酸、ベクター、宿主等)の追加》
拡散防止措置を要する実験に関する実験材料を追加する場合は、遺伝子組換え実験承認申請書【様式20-1】![]() を安全管理室宛てに郵送してください。
を安全管理室宛てに郵送してください。
《実験実施場所及び遺伝子組換え生物等の保管場所の変更》
拡散防止措置を要する実験に関する変更は、遺伝子組換え実験承認申請書【様式20-1】![]() を安全管理室宛てに郵送してください。
を安全管理室宛てに郵送してください。
《実験従事者*の追加、削除、登録内容の変更》
変更することが分かった時点で、遺伝子組換え実験従事者(届出書/変更届出書)兼教育訓練実施報告書【様式20-7】![]() を安全管理室宛てに郵送してください。
を安全管理室宛てに郵送してください。
*事前に遺伝子組換え実験従事者として登録されている者に限ります。
《実験責任者の変更》
実験責任者を変更する場合は、実験を一旦終了させ、新たな実験として申請が必要です。
※実験責任者が、旅行、疾病などの事故やその他やむを得ない事情でその職務を行うことができないときに、予め申請していた実験責任者の代理者に交代する場合は、この限りではありません。
《実験中》
実験室ならびに実験実施場所の入口付近および遺伝子組換え生物等の保管場所に、法令の定める標識を掲示してください。標識は、安全管理室に用意してありますので、ご連絡ください。
| 実験に放射性物質を用いる際の手続きについて |
SPring-8/SACLAに放射性物質(RIとしての定義量未満で、密封された状態の物)を持ち込み使用する場合、安全管理室長の許可を必要とします。定められた期日までに、必要な書類を安全管理室に提出してください。
■ 密封状放射線源持ち込み申請書 様式21〈提出:実験責任者〉
SPring-8/SACLAに放射性物質を持ち込む場合は、持ち込み予定の2週間前までに「密封状放射線源持ち込み申請書」を提出してください(原本)。ただし、使用の可否(放射能量や試料の密封状態)については、使用条件などを勘案して個別に判断しますので、あらかじめ安全管理室にご相談ください。詳細については、こちらを参照してください。
| ヒト由来材料を用いる実験に係る手続き等について |
ヒト由来材料とは、ヒトの生体および屍体から採取した組織、器官、細胞、血液(全血並びに成分血)およびその他の体液で、個人を特定できるものをいいます。ただし、標本や研究材料等として公に供給されているものは除きます。SPring-8/SACLA 利用研究課題でヒト由来材料を使用するときは、事前の承認が必要です。定められた期日までに、以下の書類を提出してください。ヒト材料が感染性を持つおそれのある場合は、様式19-1「生物実験計画届」も提出してください。詳細は、こちらのサイトを参照してください。
■ ヒト材料を用いる研究に関する誓約書 様式23-1〈提出:実験責任者〉
実験責任者の所属機関(大学であれば学部長以上の者または倫理審査委員会)が、当該SPring-8/SACLA 利用研究課題でヒト材料を用いることを承認していることの誓約を、この様式![]() を用いて課題毎に提出してください。
を用いて課題毎に提出してください。
■ ヒト材料取扱申請書 様式23-2〈提出:実験責任者〉
実験責任者は、ヒト材料を保管管理している機関(以下、「ヒト材料管理機関」)で、ヒト材料が適正に入手されたこと、およびヒト材料を研究に使用することについて承認されていることの誓約(主任教授以上の者)を、この様式![]() で提出してください。また、SPring-8/SACLAでヒト材料を取り扱う際のヒト材料管理責任者を任命してください。本書類は、ヒト材料管理機関毎に提出してください。
で提出してください。また、SPring-8/SACLAでヒト材料を取り扱う際のヒト材料管理責任者を任命してください。本書類は、ヒト材料管理機関毎に提出してください。